
「Dying Light: The Beast」では、アクション満載のRPGでカイル・クレインとしての役割に戻り、危険に満ちたキャスターウッズを戦い抜きます。最新のゲーム開発情報はこちらでチェックしてください。
← 「Dying Light: The Beast」メインページに戻る
Dying Light: The Beast ニュース
2025年
7月21日
⚫︎ テックランドは、マスコット「ビーバーのボーバー」を起用した架空の観光CM風トレーラーを公開。陽気な演出がゾンビの襲来で一転し、キャスターウッズの過酷な世界観を風刺的に表現しました。
続きを読む: 『Dying Light: The Beast』新トレーラーがビーバーのボーバーで観光パロディ(Gamingbolt)
7月7日
⚫︎ 無謀なゾンビ討伐の定型から脱却し、「The Beast」は戦略性あるパルクール戦闘と強化された敵遭遇システムでシリーズを進化させます。ティモン・スメクタラ監督はAIの向上、武器物理演算の改良、銃器の復活を明言。
従来のハックアンドスラッシュ型ゾンビゲームと異なり、本作は緊迫感ある戦闘を保ちつつ戦術的な交戦を重視。スメクタラ監督は『Dying Light 2』のシステムを発展させ、より挑戦的でやりがいのあるゲームプレイを実現した過程を語りました。
続きを読む: 殘虐性はそのままに、戦闘は戦略を要求する
- 「The Beast」が単純なゾンビ戦闘を超える理由(Game Rant)
7月1日
⚫︎ テックランドは広大だが空虚なオープンワールドではなく、密度の高い環境設計を「The Beast」で優先。スメクタラ監督は「真の没入感は地図の広さではなく、意味あるコンテンツ密度から生まれる」と従来手法との差別化を説明。
監督は『Dying Light 2』で主流迎合した反省に触れつつ、サバイバルホラー本来の雰囲気を取り戻すため、洗練されたデザインと緊迫感ある世界構築に注力していると語りました。
続きを読む: 『Dying Light: The Beast』が証明するオープンワールドの成功はサイズではない理由(Game8)
4月4日
⚫︎ テックランドは『Dying Light』本編の再プレイを推奨。「The Beast」が両作品の架け橋となる物語であることを明かしました。スメクタラ監督は「コアファンからは初代の妥協なきサバイバルホラーを好む声が多い」とファン層の嗜好の違いを認めつつ、
両作品の要素を意図的に統合し、シリーズの連続性を維持しながら多様なプレイヤーの期待に応える設計を説明しました。
続きを読む: 『The Beast』発売前に初代『Dying Light』を再プレイすべき理由(Epic Games News)
2月12日
⚫︎ 当初『Dying Light 2』のDLCとして計画されていた「The Beast」は、開発過程で完全なスタンドアローン作品へと拡大。テックランドは本作がDL2のアプローチとは異なる野心的な方向性を持つことを確認しました。
2024年ゲームズコムで最初のティザーが公開されたこの進化的ステップは、シリーズのルーツを尊重しつつ革新を続けるテックランドの姿勢を示しています。
続きを読む: 『Dying Light: The Beast』がDL2と一線を画すことで切り開くシリーズの未来(Gamerant)
-
{{'OhReungはSLC 2025で勝利を主張し、優勝者に輝いた'}}{{'彼の獲得賞品には1000万ウォンとLG gram Pro 360ノートパソコンが含まれていた'}}{{'準優勝者らにも特別賞金とLGモニターが授与された'}}{{'Solo Leveling: Ariseは最近、初の世界大会を終え、観客を魅了した見事な光景を提供した。4月12日に韓国のIvex Studioで開催されたSLC 2025では、世界中の精鋭プレイヤーたちが「戦場の時」モードで競い合った。興奮は高く、チケッ著者 : Sarah Dec 17,2025
-
ヒットマン:ワールド・オブ・アサシネーションがモバイル端末に登場します。iOS版では、エージェント47の任務へ没頭することができます。ステルスアクションでプロビデンスに立ち向かい、消えるターゲットを処理しましょう。先週末には、注目すべき主要なゲームショーケースがいくつか開催されました。ほとんどの発表はコンソールとPCを対象としていましたが、モバイルゲーミングについても重要なアップデートがありました。特に、IOインタラクティブは彼らの人気復活シリーズ『ヒットマン:ワールド・オブ・アサシネーション』著者 : Samuel Dec 17,2025
-
 Memorize General Tokugawaダウンロード
Memorize General Tokugawaダウンロード -
 Bike Hill Racingダウンロード
Bike Hill Racingダウンロード -
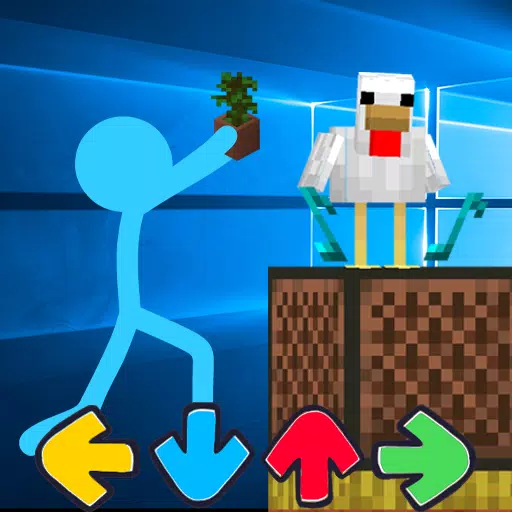 Beat Fight Stick Full Weekダウンロード
Beat Fight Stick Full Weekダウンロード -
 Shopping Rush Idleダウンロード
Shopping Rush Idleダウンロード -
 Indoor Futsal: Football Gamesダウンロード
Indoor Futsal: Football Gamesダウンロード -
 SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTHダウンロード
SCHOOLBOY RUNAWAY - STEALTHダウンロード -
 Pokellector Supermarketダウンロード
Pokellector Supermarketダウンロード -
 Run Legends: Make fitness fun!ダウンロード
Run Legends: Make fitness fun!ダウンロード -
 Tennis World Open 2024 - Sport Modダウンロード
Tennis World Open 2024 - Sport Modダウンロード -
 English Ear Game 2ダウンロード
English Ear Game 2ダウンロード












